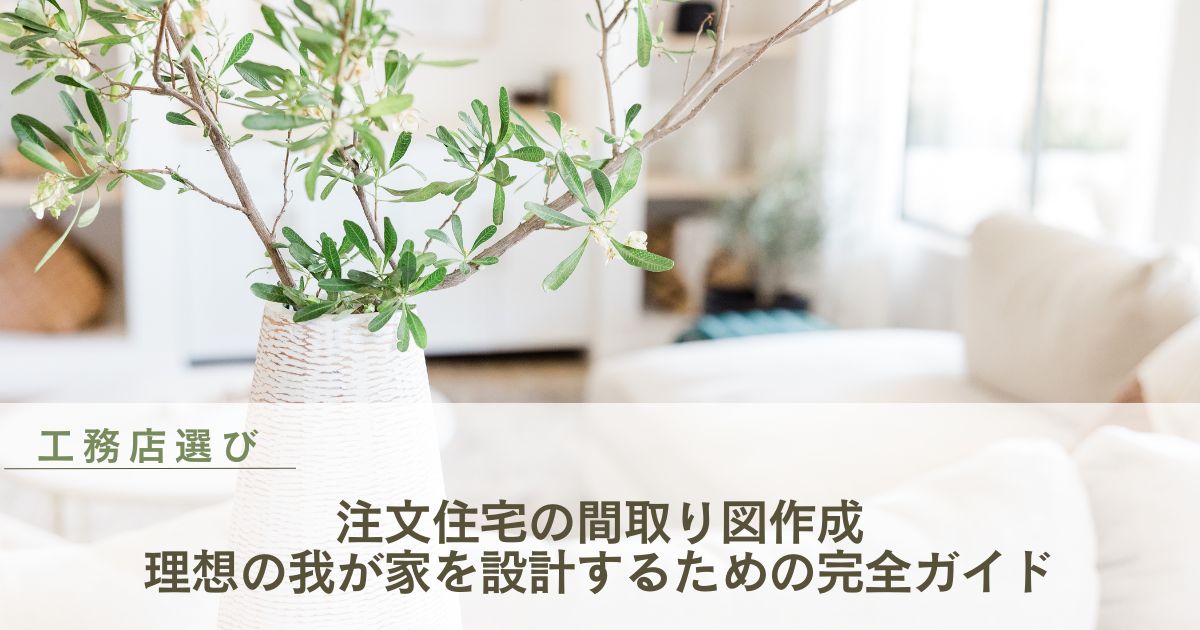「家族だけが使える特別な場所として屋上を作りたい。」
「いや、家族で使える収納として屋根裏を作りたい。」
住宅の「間取り」を考えるにあたって、屋上か、屋根裏収納か、中二階収納(ミサワホーム)かを検討することがあるのではないでしょうか?
屋根部分にできるスペース(空間)については、主に「屋上を作るか」、「屋根裏収納を作るか」の選択肢が生まれますが、「屋上」「屋根裏収納」の多くは、容積率・建ぺい率の影響を受けません。
自由に使えるスペースとしてプラスアルファで有効活用できる場所となるため、間取り作成の際にはスペースが取れるように、階段の向きや位置を調整したりベランダの位置を検討するようにしてみましょう。
本記事では、両者のメリット・デメリットを詳しく比較し、あなたの家に最適な選択肢を見つけるためのガイドをご提供します。最後に、私が選択したのは屋上だったのですが、理由と使ってみた感想もお伝えします。
はじめに 屋上スペース・屋根裏収納スペース検討の重要性について
土地と家を同時に購入する方も、家だけを建て替えで購入する方も、知っておきたいのが、建ぺい率と容積率です。
家を立てる場所の市区町村・地域によって、土地面積から建てられる「建物の建ぺい率・容積率」というものが決まっています。
「土地面積」と「容積率・建ぺい率」が決まると、建築できる建物の最大の大きさ「建物面積(建築面積)/延べ床面積(建坪)」が自動的に決まります。
最大の大きさ「建物面積(建築面積)/延べ床面積(建坪)」が決まると、部屋の大きさを含めた間取りに制限が生まれます。
部屋の大きさや間取りの工夫で満足できない場合には、土地を広くする必要がありますが、土地を大きくしてしまうと、その分土地費用と建築費用が上がってしまうため、費用が予算に対してオーバーしてしまうようなことがあります。
そのため、予算(費用)の関係からも、限られた空間を有効活用することは家を建てる上でたいへん重要になります。
あらかじめ知っておきたい、建ぺい率(建蔽率)と容積率について
購入する土地や、自分が所有している土地に対して、どれくらいの大きさの家が作れるかを知るためには、容積率や建ぺい率を理解しておく必要があります。
同じ面積の土地であっても、地域により定められている「建ぺい率・容積率」によって、建築できる家の大きさには制限があります。
建ぺい率と容積率の規制は、建築基準法により定められています。
建築基準法とは建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めた法律のことです。
また、建ぺい率と容積率は市区町村の都市計画により「13種類の用途地域」により大まかな範囲が決まり、市区町村の指定により数値(率・パーセント)が決定されています。
13種類の用途地域で建ぺい率と容積率の範囲が決まる
「13種類の用途地域」とは「計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリア」のことです。
建てられる建物等の種類や大きさなどが制限されているので、結果として地域ごとの特色や景観が生まれます。
用途地域が指定されているのは、利便性の向上や生活環境を整える目的があります。
例えば住宅の隣に大きな商業施設や工場、学校や公園がごちゃごちゃと建っていると、日当たりや騒音、公害などで住みにくい環境になってしまいます。
一方の工場にとっても、例えば大型トラックが通りにくいとか渋滞が発生しやすいなどで、効率が悪い環境になることが考えられます。
そこで国は都市の健全な発展を目的に「都市計画法」を定め、この法律に基づいて都道府県知事が「都市計画」を立てています。具体的には地域を下記の3つに分けます。
■都市計画区域とそれ以外の区域
- 都市計画区域:計画的に街づくりを進めるエリア
- 都市計画区域外:人があまりいない地域なのでとりあえず市街地化計画をしないエリア
- 準都市計画区域:人があまりいないけれど重要なので制限を設けておこうというエリア
さらに上記の1で「都市計画区域」と定められたエリアを、下記の3つに分けます。
■都市計画区域内の区分
- 市街化区域:すでに市街地を形成している区域や、今後優先して計画的に市街地化を図るべきエリア
- 市街化調整区域:農地や森林などを守ることに重点を置くエリア
- 非線引区域:計画的に街づくりをする予定だが、とりあえずは現状のままにしておくエリア
さらに、(A)市街化区域を「景観を守る」や「防火対策」など用途や目的等に応じて21地域の「地域地区」に分割します。このときの21地域の中の1つに「用途地域」があります。
13種類の用途地域
用途地域は、住居系・商業系・工業系を合わせて13種類あります。それぞれに建ぺい率・容積率の基準範囲がありますが、その範囲の中での数値は地域の指定によって決められています。
住居系
- 第一種低層住居専用地域
- 低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(商業施設がないor少ない)
- 第二種低層住居専用地域
- 主として低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(商業施設はある)
- 田園住居地域
- 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(商業施設がないor少ない)
- 第二種中高層住居専用地域
- 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(商業施設はある)
- 第一種住居地域
- 住居の環境を保護するため定める地域(商業施設がないor少ない)
- 第二種住居地域
- 主として住居の環境を保護するため定める地域(商業施設はある)
- 準住居地域
- 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
商業系
- 近隣商業地域
- 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
- 商業地域
- 主として商業等の業務の利便を増進するため定める地域
工業系
- 準工業地域
- 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
- 工業地域
- 主として工業の利便を増進するため定める地域
- 工業専用地域
- 工業の利便を増進するための地域
建ぺい率と容積率の最終的な設定数値は各市町村自治体で決まる
以下で建ぺい率、容積率の基本的な考え方や押さえるべきポイントを解説します。
建ぺい率とは?
建ぺい率とは、敷地面積に対する建物面積の割合を指します。敷地面積とは「建物を建てるための土地全体の面積」、建物面積とは「建物を真上から見たときの外周で求めた面積」です。
建ぺい率が決められているのは、敷地内に適切な空地を設け、採光や通風などの住み心地や安全性の確保を図るためです。
また、住居地域の建ぺい率は、30〜80%の範囲で設定されています。
「自分の土地で自由に立てられないのはおかしい」と感じる方もいるでしょう。
しかし、全員が建ぺい率100%の家を建てると「日当たりや風通しなど快適な住環」「防火や避難などの安全性」が確保できません。
建ぺい率の調べ方は、不動産会社やハウスメーカーが扱う土地であれば、チラシやWEBサイトに記載があります。
もしくは、市区町村への問い合わせや行政のWEBサイトで公開されている都市計画図でも確認することができます。
容積率とは?
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。
延べ床面積は「建築物の各階の床面積の合計」を指します。
1階が100㎡、2階が90㎡の場合は合計190㎡の延べ床面積です。
同じ広さの土地でも容積率が高ければ建築可能な延べ床面積が増えるため、より部屋を広くしたり、部屋数を増やしたりできます。
延べ床面積は「建築物の各階の床面積の合計」を指します。1階が100㎡、2階が90㎡の場合は合計190㎡の延べ床面積です。同じ広さの土地でも容積率が高ければ建築可能な延べ床面積が増えるため、より部屋を広くしたり、部屋数を増やしたりできます。
容積率が決められているのは、住み心地や安全性の確保だけではなく、人口密度のコントロールをするためでもあります。
容積率に制限がなければ「戸建住宅が並ぶ土地に高層マンションが建築され住み心地が悪くなる」ことや「人口増加による交通渋滞や電力消費、下水処理などへの負荷」が考えられるでしょう。
調べ方は建ぺい率と同じく、不動産会社やハウスメーカー、行政への問い合わせやWEBサイトで都市計画図を確認することができます。
屋根スペースを活用する重要性
地域により、敷地面積に対しての容積率・建ぺい率が決まっているため、多くの住居用途地域では敷地いっぱいには建物は作れません。
ところが、建築基準法上、屋根裏収納は「物置」として扱われるため、延床面積に算入されません。
部屋としてはみなされないため、建ぺい率や容積率の計算に含まれません。
固定資産税や保険料から見て、お得なスペースになります。
見積もり図面を見てびっくり!敷地面積いっぱいに家を建てたいのに建てられない理由
見積もり図面作成時に「あれ?もっと大きい建物にできないの?」と思うことがあります。
これは、建ぺい率や容積率によって、建物の大きさに制限がかかっているためです。
また、その他にも、建物にかかる制限としては以下のようなものがあります。
- 道路斜線
- 道路に面した建物の高さを制限するルールで、建築基準法に基づいています。
道路への日照斜線制限になるため、「建物の形状や高さ」、「道路から建物までの距離」を一定程度制限されます。
- 道路に面した建物の高さを制限するルールで、建築基準法に基づいています。
- 北側斜線
- 北側斜線制限とは、敷地の北側隣接地の日照を確保するためのもので、北側の前面道路の反対側の道路境界線または北側隣地境界線に面した建物部分の高さの制限です。
- 採光
- 建築基準法で「採光」というと、第28条「居室の採光及び換気」のことを指します。
建築基準法によると、住宅におけるリビングや寝室、あるいは、学校の教室など、人が長時間過ごす居室においては、居室の床面積に対して一定の面積の「採光のための窓その他の開口部」を設けなければならない、とされています。
リビングやダイニング、キッチン、寝室などの間取りを設計する際には、それぞれの床面積に対して窓の面積(採光面積)を計算しなければなりません。建築基準法に適合した設計をしなければ、確認申請が認められず、住宅を建てることができません。
- 建築基準法で「採光」というと、第28条「居室の採光及び換気」のことを指します。
- その他
屋上や屋根裏収納は、延べ床面積にカウントされないため、容積率に影響を受けない
斜線規制(道路斜線・北側斜線)や採光の規制については、ご近所や立地によりどうしようもないものですが、屋上(ルーフバルコニー)や屋根裏収納については、一般的に延べ床面積にカウントされません。
そのため間取りや家の形によって、自由に設置が可能です。
最大の屋上スペースを検討しておくと、最大の屋根裏収納にできるスペースにもなる
間取りや家の形を検討する上で、屋上(ルーフバルコニー)や屋根裏収納のスペースを最大限大きくできるようにしておくと、プラスアルファの住環境や収納スペースとして有効活用ができます。
屋根スペースをどうするか?【屋上編】
屋根スペースの有効活用時、屋上にするには向き不向き・メリット・デメリットがあります。
屋上が適している場合
- アウトドア活動を楽しみたい家族
- 園芸や家庭菜園に興味がある方
- 洗濯物を外干ししたい方
- 太陽光発電を検討している方
屋上を選ぶべき場合
- 十分な予算がある
- アウトドアスペースを重視
- 環境への配慮を重視
- 定期的なメンテナンスが可能
メリット・デメリット
- 空間の有効活用
- アウトドアリビングとしての活用
- 洗濯物干しスペース
- 家庭菜園やガーデニング
- 環境への配慮
- 太陽光パネルの設置が容易
- ヒートアイランド現象の緩和効果
- 断熱効果の向上
- 資産価値の向上
- 不動産経済研究所の調査によると、屋上付き物件は平均で5-8%の資産価値上昇が見込めるとされています。(出典:不動産経済研究所「住宅価値評価レポート2024」)
- コストと維持管理
- 防水工事が必要
- 定期的なメンテナンスコスト
- 防水層の寿命(15-20年)
- 安全性への配慮
- 手すりなどの安全設備が必要
- 子どもがいる家庭での注意点
屋根スペースをどうするか?【屋根裏収納編】
屋根スペースの有効活用時、屋根裏収納にするには、以下のような向き不向き・メリット・デメリットがあります。
屋根裏収納が適している場合
- 収納スペースを重視する方
- メンテナンスの手間を最小限にしたい方
- 初期コストを抑えたい方
- 季節品の収納が必要な方
屋根裏収納を選ぶべき場合
- 実用的な収納スペースが必要
- メンテナンスの手間を抑えたい
- 初期コストを抑えたい
- 収納の使い勝手を重視
メリット・デメリット
- コスト効率
- 初期投資が比較的少ない
- メンテナンスコストが低い
- 実用性
- 季節物の収納に最適
- 室内からのアクセスが容易
- 温度変化が少ない
- 空間の制限
- 屋根の形状による制約
- 天井高の制限
- 収納以外の用途に制限
- 温度・湿度管理
- 夏場の高温対策が必要
- 結露対策が重要
私の場合は屋上を選択!間取りをどうしたか?
通常あまり選択肢には上がってこないかもしれないのですが、2020年当時、私が選んだ建築会社(桧家住宅)では、2階建て建築物の「上」を屋上にするのか屋根裏収納にするかで、建築費用が同じでした。
そこが、桧家住宅を選んだ決め手になった部分もあるのですが、我が家は、「屋上と屋根裏収納」の選択にあたり、「屋上」を選択しました。「屋上」を選択した立場から感想はこんな感じです。
ああ、うちは元々収納スペースが少なかったから屋根裏収納にすればよかったかな?
でも…、収納は余計なものを持ちすぎなければ抑えられるし、屋上に登ってご近所さんの家々を上から眺めるのって悪くないなぁ
最後に、選択にあたっては以下の点を考慮することをお勧めします:
- 家族構成と生活スタイル
- 予算(初期費用・維持費用)
- 住宅の立地条件
- 将来的な使用計画
あなたの暮らしに合った最適な選択ができることを願っています。